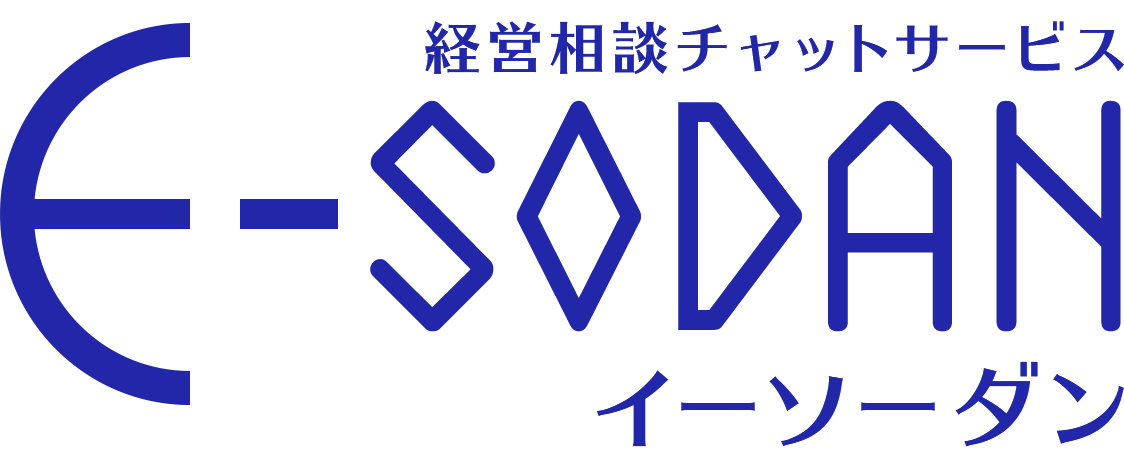昨今、環境問題などESGに配慮した事業を行う企業に対する「ESG投資」が話題となっている。一方で実態は異なるのに、投資家らを意識して企業が環境に配慮していることを装う「グリーンウォッシュ」の課題も指摘される。そうした中、存在感を放つのが、中立の立場で企業の経営体制を評価する「格付け機関」だ。その格付け機関の中でも、「Sustainalytics」は国連が持続可能な開発目標 (SDGs)を発表した2015年よりもずっと前から、環境影響によるリスク情報や評価を提供し続けてきた。1992年に創設されて以来、ESGのコーポレート・ガバナンスのための調査、レーティング、分析などを手掛ける大手 ESG 評価機関として、世界中の投資家の投資戦略をサポートしてきた、いわばESGレーティングの「老舗」機関。更に、現在ではグリーン、ソーシャル、トランジションボンド等のサステナブル・ファイナンスに対する外部評価を行うサービスも展開している。欧米・北米を中心に世界で17の拠点を有し、1200人以上のスタッフを抱え、依然、その規模を拡大し続けている。2016年10月に開設された日本法人で働くお二人に、その組織のミッションや風土を伺った。
ゲストのご経歴

朝妻 弥生様
(サステイナリティクス クライアントリレーションズ/ディレクター)
ジャーディン・フレミング証券東京支店(現JP モルガン証券)を経て、野村證券シンガポール/香港/ロンドン現地法人でアジア株式リサーチセールスとして、グローバルの機関投資家向けのアジア株式業務に長期に渡り携わる。サステイナリティクス・ジャパンには2019年に入社。クライアントリレーションズとして、ESGリサーチの機関投資家向けセールスを担当。現在、日本国内外の多くの投資家や金融機関のESG投資のサポートに従事。

兼松 浩介様
(サステイナリティクス コーポレート ソリューションズ/アソシエイト・ディレクター)
2021年に入社し、コーポレートソリューションズ・チームの日本リーダーを務める。サステイナリティクス入社以前は、ボストン コンサルティング グループ及びA.T. カーニーにて金融・保険業界を中心に全社改革、新規事業、営業・マーケティング、サステナビリティ戦略などの多数プロジェクトを遂行。また、ワシントンD.C.の世界銀行本部及び気候投資基金(Climate Investment Funds)にて、途上国・新興国向けのマクロ経済分析・政策提言や気候変動対策への資金供与(グリーンボンドなど)に関する業務に従事。東京大学教養学部(国際関係論)卒業、コロンビア大学修士(公共経営)。
ーどんなサービス・プロダクトを提供されていらっしゃいますか。
朝妻様)
クライアントリレーションズという部門で、機関投資家に向けたESGリスクに関する様々なソリューション提供しています。一番の主力商品は「ESGリスクレーティング」で、企業に対しESGのリスク評価を行うプロダクトです。投資家が投資先の企業の財務リスクを理解できるよう設計されています。ほかにも国のリスクや、企業のカーボン削減への取り組みを評価するプロダクト、また、企業が人権に反していないか、武器製造に関わっていないかなどのスクリーニング評価をするプロダクト、企業の不祥事を追うプロダクトもあります。他には、投資家が投資先の企業とのエンゲージメントをお手伝いをするスチュワードシップサービスも行っています。
兼松様)
私は、事業会社や金融機関をお客様とするコーポレートソリューションズという部署で、企業がグリーンボンドや社会貢献に寄与することを目的としたソーシャルボンドを発行するときに、そのボンドが「国際的な基準や市場慣行を満たしている形で発行されるボンドである」という意見を示す「セカンドパーティーオピニオン」=SPOを提供しています。企業がサステナビリティに寄与する事業活動に使うお金を調達したいときに、国際的に見て投資家の期待する効果につながるプロジェクトであるか否かをチェックし、オピニオンを書く仕事です。対象となる金融商品はボンドが中心ですが、ローンもあります。たとえば最近ですと、ESGやサステナビリティに関する野心的な目標の達成に応じて、企業が通常よりも有利な金利で資金調達できる「サスティナビリティ・リンク・ローン」という商品も出てきており、そのローンが環境や社会にとって良い形で使われる得るのかについてのオピニオンも書いています。
ーSPOとはどんなものでしょうか。
兼松様)
サステイナリティクスのSPOは、資金調達者である企業が策定するフレームワーク、特にボンドもしくはローンからの調達資金の活用や管理方法が広く一般に認められた市場原則(グリーンボンド原則やグリーンローン原則など)及び市場慣行や投資家からの期待に沿っていることを確認し、投資家に対して示す意見書です。あくまでも中立的な立場でのオピニオンであり、助言やコンサルティングではありません。あくまで、企業ではなく投資家に対し、我々の意見と正しい情報を提供することが目的です。弊社ではインベストサイドもコーポレートサイドも投資家との関係を最も重視しており、その関係の中でサステナブル・ファイナンスの市場を創ることを目指しています。
ー2016年に日本法人を立ち上げられた経緯はなんでしょうか。
朝妻様)
世界最大の年金基金であるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が各投資機関にESG投資を義務付け始めたことにより、投資家がESGの概念を投資に組み入れ始めたのがその時期で、そこからESGのブームが起き始め、弊社のような機関も投資家から頼られるようになり日本に拠点を構えました。
ー最近のセールスの伸びはどのくらいですか。
朝妻様)
伸びは著しく、私が入社した2019年からの2年間でも、新規セールスが約3倍になっています。投資機関も、日系で20社ほどだったのが、30社以上になっており、それがここ1年半くらいで起きています。
会社自体も、人員が私の入社時点の650人から1200人以上に増えており、2年間で2倍くらいになっています。
兼松様)
市場が伸びているので、早急に優秀な人に入ってもらうという「供給サイド」を埋めていく必要があります。
ーグローバルの市場と比べると日本はどうでしょうか。
朝妻様)
ESGの考え方自体が欧州から来ているので、欧州発で色々なものが始まり日本がキャッチアップしている状況ですが、そのラグがどんどん埋まっている気がします。必ず欧州で起こったものと同じ波が日本にも来るので、アンテナの高いお客様は欧州を常に見ています。
兼松様)
弊社のビジネスの拡大をお伝えする前提として、市場自体のトレンドを共有させてください。グリーンボンド発行のグローバル市場の規模は、対前年比60〜80%の伸びと言われています。日本も同じくらいの伸びです。菅前首相がカーボンニュートラル実現を表明して以来、グリーンボンドを必要とする事業がどんどん立ち上がっています。たとえば2021年で発行額が一番大きかったNTT様のグリーンボンドですが、本業である通信事業のエネルギー効率を高める技術を開発・普及を中心とした資金使途で総計約5000億円規模の調達をされました。本案件のSPOも弊社が作成・提供させて頂いております。また、債券発行市場全体に占めるグリーンボンドの割合は、まだ10%以下ですが、今後更に増える余地があると考えられ、企業の活動自体も環境保護や気候変動対策につながるビジネスへの変革や新規事業立ち上げのために行う債券調達はグリーンボンドでおこなう、という形になるのがより普通になるのではないでしょうか。理論上、債券発行体がグリーンボンドを“Self-label”の形で発行することもできますが、投資家が安心してグリーンボンドを購入するためにはセカンドパーティーなど外部評価が欠かせませんので、グリーンボンドの発行と同時にSPOが必要とされる状況は続いていくと思います。サステナブル・ファイナンスとしては、グリーン、ソーシャルに加えて、まだ黎明期ではありますが日本政府が推進をしているトランジションファイナンスも広がってくると思われますので、我々のサービスについて引き続き大きな成長・拡大を見込んでいます。
ー御社の活動の実績はどういったものがありますか。
朝妻様)
弊社はESG評価機関として、約30年の実績があります。私たちはESGのリーダーであるという自負を持っており、業界内でもそういった評価をされています。サステイナリティクスという名前はブランド力があると思います。世界有数の機関投資家クライアントがいらっしゃり、そうしたお客様のESG投資のお手伝いのため、ESGリサーチやデータを提供し、我々としても持続可能な世界に貢献するというのがミッションです。
兼松様)
ESG評価機関としては30年の歴史があって、投資家やキャピタルマーケット、政府の関係者からの信頼やブランドはすごくあると感じます。グリーンボンドは約10年前に新しく出た金融商品ですが、弊社は2014年にはSPOのビジネスをスタートさせており、ESG債が生まれたのとほぼ同じタイミングで参入しています。7年間事業を行い、既にグローバルの累積で800件のSPOを提供し、トップシェアを維持しています。世界の様々な国の各産業のトップ企業のESG債発行のお手伝いさせていただいていることは社員として大変誇らしく思います。創業者であるMichael Jantziは30年前にESGにフォーカスした会社を立ち上げて、非常に先見性があるなと思います。
朝妻様)
世界に17のオフィスがありますが、社員は常に増えています。採用ペースが大変速く、世界的に人材を見つけるのがチャレンジングな状況です。ESGは新しいコンセプトがどんどん登場していて、プロダクトの数もどんどん増えています。リサーチの質を保つためにも人員を増強していく必要があると感じます。
ーどんな人材が御社で活躍できそうですか。
兼松様)
当社は、より公正で公平な世界経済に貢献するという同じ情熱を持った人々のコミュニティであることを誇りにしています。そのため、より持続可能な未来に向けた私たちの価値観やビジョンを共有できる方を常に求めています。さらに、知的好奇心が旺盛で、対人関係や協調性に優れた人材を求めています。また、ESG分野の急速な成長と当社の急成長を踏まえた時に、適応力の高いチームメンバーも求めています。
入社後のトレーニングプログラムや、OJTもありますが、変化の激しい市場で展開している会社なので、そういう変化を楽しめる人がいいと思います。新たなソリューション、プロダクトも日々出てきますので、学んでいく意欲があるかどうか。これからグリーン、ソーシャルという基準も不変なものではなく、投資家が求めることや企業が新たに生み出す事業の内容に応じて変わってくるので当社が参照する自社独自の基準(タクソノミー)も進化していきます。そうした変化についていき、プロダクト・サービスをデリバリーできる人材はウェルカムです。コンサル、金融業界に限らず様々なバックグラウンドをお持ちで、ESGを積極的に学んでいく意欲を持って仕事を進めていくエネルギッシュな方が向いていると思います。
朝妻様)
適応力が高く、変化に耐えられるが重要です。ESGに興味がないと辛いでしょう。逆にESGに興味があれば、とことん学べるので非常に面白いです。自分で考えて行動できる、むしろ無いものを作り上げるくらいの気概を持ったアントレプレナーシップがある人材は活躍できると思います。
兼松様)
当社は30年以上の歴史のあるエスタブリッシュな企業という側面もありますが、ベンチャー企業で事業を作っているようなスピード感があります。私自身も、伸びていく市場に自ら関与してその成長に貢献しているということにやりがいを感じているので、近いマインドセットの方々には楽しめる環境ではないかと思います。また、国内市場も伸びていますが、海外の各地域でも市場は伸びていますし、新たな市場のルール形成の動きもありますので、その流れにも関わっていきたいというグローバルマインドのある人なら、なお面白いと思います。“この大学のこの学位が必要”という類いのビジネスでもないので、ESGやサステナブル・ファイナンスに対する思い入れのある人が第一人者になることを目指すような場だと感じています。
ー語学力は重要ですか。
兼松様)
私は日常的にオーストラリア人やカナダ人などの上司と作戦会議をしたりプロジェクトの進捗をチェックしてもらったりするので、スムーズにやり取りをするなら、英語がしっかりできることが望ましいです。
ただ、日本チームのお客様は日本企業が中心なので、英語だけでなく、大手の機関投資家や、大企業を相手に仕事を行う最低限のビジネスコミュニケーションが必要だと思います。
ーお二人はどんなキャリアを歩んでこられましたか。
朝妻様)
私はずっと証券会社でアジア株式を20年以上取り扱ってきました。シンガポール、香港、ロンドンで営業をやり、2年半前に会社を辞めました。ここから先に投資に関わるために何を仕事にしようか考え、ESGを学ぶべきだと思いました。ESGについて学べる場所は限られており、親しかった機関投資家のお客様にご紹介いただいて、ご縁があって入社しました。機関投資家向けの営業に関わっているという点では首尾一貫したキャリアです。自分としてもESGに関わるお仕事であれば社会に貢献できると思いました。
兼松様)
これまではコンサル、国際機関で働いてきました。振り返ってみると、結果として、比較的長らくサステナビリティやESGの分野に携わってきましたが、新卒で就職活動を行っていた2000年前後には、今やっているような仕事はありませんでした。そういう意味で、今20〜30代の人は若い頃からサステナビリティをお仕事にできて羨ましいと思います。
私が今の仕事を志向する原点について、少し長くなりますが経緯をご説明します。25年前のことですが、大学の900番教室の前で何気ない会話をしている中で経済学部の友人が「今後は環境影響への取り組みが評価されて企業の株が売買される世界になる」という話をしていたのを今でも鮮明に覚えています。その時、環境とビジネスがつながるという面白い世界観だなと思いました。また、同じ年にアジア通貨危機があってアジアの発展途上国で社会的混乱が起き、「必要なところに必要なお金が回らなくなることはすごく不幸なことだ」と強く感じ、将来起こる金融危機を防ぐような仕事に関わりたいと思っていました。このような思いを持ちつつ、2015年前後に世界銀行で気候変動関連の仕事をしていた時に、グリーンボンドという金融商品に触れ、民間の資金や企業の事業活動を活用して、気候変動という地球規模の課題解決に貢献すること、本来必要なところに必要なお金が回る仕組みを作ることは、25年前に抱いた思いを実現する仕事になり得ると感じました。それらの体験が、今の仕事に携わることになった主な2つが原点です。
一方で、最初に申した通り、20年の社会人経験の中で常時サステナビリティやESGに関われたわけでなく、今持っているようなキャリアの方向性を得ることに至るまでは、様々もがいていた気がします。昔から各勤め先で、少しでもサステナビリティ、ESG、気候変動などに関わることは僅かな機会でもやりたいという思いを持ち、その時、その持ち場で最大限ベストを尽くしていたことで、今やっと“connect the dots”の状態になっているのかなと思います。
新卒で勤務した外資系コンサルティングファームのA.T. カーニーでは、社会人としての基礎体力を身に付けるような期間だったと思いますが、同時にサステナビリティ経営というテーマに初めて触れる機会を得た場でもあったと思います。2007年頃に当時のグローバルCEOが「サステナビリティ戦略」というテーマで講演などをしているのを見て、面白いと思いました。彼はアメリカ民主党に近く、若き日にJoe Bidenのアドバイザーもしていたような人なので、特にこのようなトレンドへの感度が高かったのだと想像します。私は、当時の日本代表に「いくつかのクライアントにサステナビリティ戦略のプロジェクトを提案したい」と訴え、サポートを頂きました。しかし、当時のビジネスコミュニティでは、まだ機が熟しておらず、芳しい反応は得られませんでした。
その後世界金融危機が起こり、それまでの強欲な資本主義ではない新しい金融の仕組みができるのではないかと仮説を持ち、そういうことが決められるのはワシントンDCだろうと思い世界銀行に転職しました。世銀内では様々な部署で働いたのですが、2015年より気候投資基金(Climate Investment Funds)に勤務することになり、そこでグリーンボンドを発行するスキームを考えるファイナンシャルモデリングを行う仕事をやっていました。2015-16年にパリ協定が締結及び批准されという追い風の中、世界銀行の気候変動グループも我が世の春を謳歌するような雰囲気で、携わっていた総額5,000億円規模のグリーンボンドの案件もスムーズに前に進む感じでした。しかし、いざプロジェクトのGOサインを出す理事会の1か月前に関係国での政治状況が大きく変化したことで、一気に風向きが変わりプロジェクトが止まってしまいました。本案件は、2016年から5年後のCOP26でやっと案件発表に至りました。私は、当時気候投資基金内でこの案件を前に進めるよう様々動いていましたが2018年頃にはかなり難しいと悟り、40代に差し掛かるキャリアをより前向きに築ける場を模索し始めました。
世銀の気候投資基金で気候変動の世界の”天国と地獄”を味わった経験から、「時の政権・政治に左右されることなく、民間主導で気候変動への取り組みが進められることが重要」という思いがあり、そのような影響力を発揮できる会社として、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)に転職することにしました。BCGではソーシャル・インパクトチームの日本での立ち上げに関わったり、金融機関のお客様を相手にサステナビリティ経営やカーボンニュートラルに関わるプロジェクトを行ったりして、充実した時期を過ごしていました。一方で、気候投資基金でグリーンボンドを発行まで持っていけないかったことが自身のキャリア上の”unfinished business”としてひっかかっていたのと、広い気候変動という分野の中でもファイナンスを軸にした経験を積みたいという思いに駆られ、国内外でサステナブル・ファイナンス市場の急成長が予見された2021年初頭にサステイナリティクスに転職することを決めました。投資家や証券会社、事業会社の間に立つ中立的な評価会社でグローバルナンバーワンの会社に行くことは自分のキャリアに大きくプラスになると思うと同時に、年齢的にも市場の成長フェーズ的にも、これを逃したら次のタイミングないという気持ちで、思い切ってリスクテイクした感じだったと当時の心境を回想しています。
ー当初から環境ビジネスでご経験を長らく積んでこられたんですね。
兼松様)繰り返しになりますが、結果としてはそうですね。せっかくキャリアの様々な経験が繋がってきたので、これから新しい金融のメインストリームになる可能性を秘めたサステナブル・ファイナンスを健全な形で普及させたいと思っています。この数年の間に民間主導の自律的な市場のメカニズムとして確立されていくと、どんなに政治対立があったとしても、サステナブル・ファイナンスが回っていく環境を作るのに貢献できたらと思います。気候変動の世界は、パリ協定締結・批准当時の盛り上がりから様々アップダウンがありましたが、サステナブル・ファイナンスに関わる者として今がまさに勝負どころだという思いでいます。いずれにしても、俯瞰的に見ると、気候変動等の地球規模の課題に対して公的な財政施策ではは限界があり、機関投資家等、民間のお金がサステナビリティ領域に回っていくことの必要性は変わりません。主要先進国が財政赤字である一方、機関投資家のアセット規模はどんどん大きくなっている状況がそれを示しています。いかにキャピタルマーケット、機関投資家に貢献してもらうのか、その橋渡しが我々の仕事だと考えています。
ー御社を一言で言うならどんな会社でしょうか。
兼松様)
ビジネスの大学・学位がMBAなら、当社はESGの“学位”が取れる大学のような側面があると思っています。実際の大学でESGを包括的に学べるところはハーバードにも東大にも今のところありません。30年の蓄積があって、グローバルのマーケットリーダーであるサステイナリティクスでは、ビジネスを回していくことと同時に、ESGやサステナブル・ファイナンスを体系的に学べる環境でもあるため、3〜5年働けば、その経験・実績が一種のMBAのようになるのではないかと思っています。ESGのMBAを取るような感じです。
朝妻様)
入社する時フランス人の上司に、ESGの勉強ができるかどうかで会社を決めたいと相談したら「サステイナリティクスでは死ぬほど勉強できるよ」と言われました。逆に勉強しないとキャッチアップできない世界です。
兼松様)
同僚との会話一つとってもESG分野の最先端の知識を学び吸収できていると感じます。ヨーロッパとアジアと北米の同僚と各国政府のタクソノミー策定の動向について意見交換しました。それらの動きを踏まえつつ、当社のタクソノミーは現在どうなっていて、今後どう変わっていくのか思考を巡らせるのも知的な刺激があります。そういう日々の仕事を通して、ESGやサステナブル・ファイナンス分野での第一人者になれると最高ですね。
ー次のキャリアの展開はどう考えていますか。
兼松様)最大かつ先進的なマーケットを視野に入れて、次はヨーロッパの本社に行きたいと思っています。
朝妻様)サステイナリティクスは自由で、やる気があって行きたい国があればどこでも働けるチャンスはあります。アジアの市場も急速に成長をしており、日本はアジアの一部でしかありませんので、私も将来的にはAPAC市場で再び働きたいです。
ー業務をやってこられる中でどのような時にやりがいを感じますか。
朝妻様)機関投資家と20年以上話す中で、以前は機関投資家の考えていることはいかに株式市場でお金を儲けるかということだと思っていましたが、実はそうではなく、彼らもESG投資を通して世界にポジティブなインパクトを与えようとしている、そうした側面が見えたことは新たな発見でした。投資はただ儲けるだけではなく社会にインパクトを与えることだということが実感できる時が面白いです。
前は私も株式市場においては利益しか見ていませんでした。今は機関投資家もどんどんマインドセットが変わり、以前であればESG投資しても儲からないと言っていたのが、そうは言ってられない時代になってしまいました。ポジティブなインパクトを世界に与えていきたいという思いが皆にあり、さらに利益が出たら素晴らしいと、両面で見えるようになったというのが私にとってもプラスです。
兼松様)
サステナブル・ファイナンスの市場はグローバルでも日本でも盛り上がってきており我々の主力商品であるSPOの提供を通して、市場を作るという点にやりがいがあります。「この事業は、市場が求めるこの基準・閾値を満たしているのでグリーンだ」という事例を通して、だんだんスタンダートが世の中に伝わる形で健全な市場の形成に貢献できていることを実感します。
今後進めたいと考えているのは、政府の関係者との対話を増やしていくことです。サステナブル・ファイナンスには、環境省、金融庁、経産省、また日本銀行も関係していますので、我々のグローバルや日本国内での長年の知見・経験を還元する形で、対話を通して一緒に健全な形の市場を作っていけたらと思っています。
ーグリーンウォッシュについて問題視する声もありますが、御社の存在意義はどこにありますでしょうか。
兼松様)
「健全な形の市場の形成」という言葉を何度も使わせて頂きましたが、まさにグリーンウォッシュは防ぎたい問題です。投資家に信頼できる情報を提供し続けるところが我々の存在価値です。コーポレートソリューションズのビジネスでいえば、グリーン適格ととは言えないボンドに我々は意見書を付けられませんので、この段階で一定のグリーンウォッシュの可能性を排除していけます。また、我々がグリーン適格であるとその時点で認めれば、投資家も安心してボンドを購入し、企業側も事業を進めることができます。また、アニュアルレビューというサービスを提供することで、事前に約束したグリーン適格な事業と違う事業にお金を回していないことを確認することで、債券発行後もグリーンウォッシュがないことを担保できると考えます。正しいところに正しいお金を回すことが重要なミッションであり、信頼と実績が当社の強みです。
朝妻様)
我々の知見がESGにおけるスタンダードだと思ってくれる投資家は多いです。
兼松様)
この業界に関わっている重要な意思決定者である機関投資家、政府関係者、事業会社、証券会社の方々からもサステイナリティクスがこの分野のフロントランナーと認識していただいているので、ビジネスがやりやすいと感じます。同時にその信頼を維持・発展させていく責務を感じます。
朝妻様)
ESGという世界では我々はリーダー的な存在です。それを味わいたい人、やる気の若者に入ってきてほしいと思います。
兼松様)
サステイナリティクスのブランドに胡座をかくことなく、それをテコにして、ビジネスを作っていきたい人や、政府と政策対話をしたり、機関投資家や事業会社と信頼関係をつくりビジネスを大きくして、新サービスを提供していこうという気概のある人と一緒に働きたいです。
ーお話をお聞かせくださり、ありがとうございました。

Sustainalytics Japan Inc.関連求人情報
今回特集しましたSustainalytics Japan Inc.様の求人をご紹介します。
ご興味がある方は、下記ボタンよりぜひご応募ください。
■求人:
外資系ESG 評価機関でのクライアントサービス Associate/Senior Associate
■年収イメージ:
経験と能力により考慮します。(年収イメージ600万円〜800万円)
■業務内容:
Working collaboratively to grow and strengthen client relationships across a portfolio of Japanese and global institutional and retail investor clients. Ensuring that our data and research content and delivery meets clients’ needs. Providing effective customer support, responding to queries and seeking feedback. Guiding clients through complex concepts in a succinct and clear way. Supporting clients’ ESG strategy development by providing advice and guidance on market best practices; Developing detailed understanding of Sustainalytics research and services, our clients and the financial and ESG market. Staying on top of client and market developments, identify and share opportunities with internal teams. Collaborating with colleagues across different teams including sales to ensure opportunities are managed efficiently effectively, and research and data delivery to enhance the client experience.
■必要スキル:
QUALIFICATIONS
The ideal candidate needs to be a real team player with strong client service skills and a good understanding of the investor landscape and responsible investment trends. The ideal candidate will have the following qualifications:
2-5 years in a client relationship role in in the investment industry.
Demonstrated knowledge and understanding of financial services and ESG.
Strong client servicing and commercial skills.
Clear communication and presentation skills.
Ability to take the initiative and think creatively and proactively.
Experience and an aptitude in leading projects from start to finish with little oversight.
Ability to understand and present complex products.
Proficiency in English and Japanese.
Commitment to sustainability and alignment with the companys’ mission, vision and values.
コトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。
最新の採用動向や非公開求人情報などの情報提供をさせていただきます。
また、ざっくばらんな意見交換・ご相談をさせて頂きながら、理想のキャリアを歩むためのアドバイスをさせていただきます。 お気軽にご相談ください。